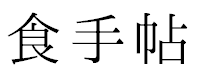2020/8/10
座布団がほしい、とずっと思っていた。椅子を使っているけれど、表面がつるつるしているので夏でもお尻がつめたくなる。はなれの小屋は床座りなので、お客さんの足が痛いだろうなあ、と思い続けて4年。だいたい欲しいと思う座布団がほとんどない。あるのは昔ながらのものだったり、大きすぎたり、分厚すぎたり、デザインが好みでなかったりとなかなか悩ましい。ごくたまに「あ、これいいな」というものがあったとしても、それらはほぼ間違いなく上等かつ高価で(京都の老舗の座布団屋さんのものとか)、1枚なら思いきって買えないこともないかもしれないが、5枚購入することは難しい。
悩みは他にもあった。15年以上も前に手に入れていた穴だらけになってしまったカシミアのガウンと、オーガニックウールの大判の布をどうすべきか。ガウンは一生ものと思って購入したが、冬の寒い時期に毎日家で羽織るなど酷使した結果、おしりの部分に大きな穴が開いてしまった。袖口は幾度か修理したがいまや修復不可能なほどに伸びきってしまい、さらにはあちらこちらに無視できない大きさの虫食いの穴ができてしまっていた。加えて当時20代だったわたしが、憧れの人から直接買わせてもらった、という経緯もあった。物に対する思い入れは薄い方だと思うが、ぼろぼろになったからといって処分する気にはなれなかった。この素材をなんとか生かすことはできないか。そこで思いついたのが、それを座布団の中綿にしてもらうというアイデアだった。
もう着なくなった良い素材のコートやセーターの始末に困っている人や、穴のあいたブランケットをどうしようかと考えあぐねている人はある程度の数いそうだから、わりに需要があるのではないかと踏んで、折に触れて布まわりの仕事をしているひとにアイデアをもちかけたが、みんなうーん、と首をかしげるばかり。手元にある不要な素材から必要なものが生まれるなんて、いい考えだと思うんだけどなあ、しかし作り手としてはいろいろとハードルがあるのかもしれない(なにしろ人から手渡された様々な素材で作るのだから)と感じながら数年がたった。
冬ものを洗って収納しなければ、と思った初夏のある日、洋服の仕立てをお願いしている友人にこの話をもちかけた。座布団を作ってほしい。中の詰め物は手持ちのものをつかって、カバーは別で洗えるようにしたいんだけど、と伝えると、彼女は「おー、それやりたいかも。カバーは最近わたしの染めた布を組み合わせた感じのものでもいい?」と言ってくれた。思い続けたそのさきに、タイミングがやってくる。 物事は動くときにだけ、動き出すのだ。
さっそく箱にガウンと布を詰めて送ったのが5月ごろだっただろうか。物事が動き始めたことに、すっかり満足してしまい、その後のやりとりのスピードは停滞、出来上がりは秋頃かな、とぼんやりと思っていた。
そんなある日、紙包みが届いた。開くと直しをお願いしていた寝間着2着と、そして座布団が入っていた。夏の間にできるとは思っていなかったので驚きつつ、目に入る色彩と意匠に理想以上の理想を見る。
添えられたうつくしい手紙には「座布団はカバーが外して洗えるように、そして、がしがし洗ってもほつれてこないように、パッチワークのつなぎ目はふくろ縫いというぬいしろが表面に出ない方法にしています」とある。色鉛筆で染められた布の図解。鮮やかな黄色は棕櫚(しゅろ)、軽やかなうす緑は葛、あわい紅色は車輪梅、大待宵草(おおまつよいぐさ)のあずき色と虎杖(いたどり)のぶどう色、ニュアンスのある茶色は胡桃。どれも彼女が自分で採取したもので染めたものだ。
あまりにうつくしくて、まるで作品のようだから、その上に座ってしまうのがためらわれた。が、これはあくまで座布団、実用品は使ってこそ。思い切ってそのまっさらな座布団に腰をおろした。安心感のある厚さと安定感(中にはわたしが送った布が入ってる)、それでいて軽やか。
色は、目に見える「色」以上のものを含んでいるように思う。それを見たり、使ったりするひととの間に生まれるエネルギーや力、のようななにか。この色がすき、ということはその人の体がその色と響きあいやすい、ということなのかもしれない。人についても同じことが言えると思う。
それぞれが、「生まれながらの色」をベースに持ちつつ、その時そのとき刻々と変化する「いまの状態の色」との2種類を持っているようにも感じる。マーク・ロスコの絵のように、上下2色にわかれているイメージ。
自然の素材からうまれた色は、その意味ですでに多くを含んでいる。素材の育った土地、水にうつされた色、そしてそれを布へ転写するプロセス。素材は近所に自然に生えているものを使っているという。そのことが、「この色を染めたい」というよりも「これで染める」という姿勢を生み出してゆくのだろう。
最初から最後まで、ひとりの手で。その行程には、果てしない時間が費やされたことだろう。植物的な雰囲気をまとった彼女のことを、これまでは布の人、と思っていたが、もしかしたら、ほんとうは染めのひと、なのかもしれない、とふと思う。自宅で育てた蚕(マンションで!)で紡いだ絹糸を自ら染めたもので上衣を繕ってもらったこともある。紡ぎも、染めも、縫うことも、古来からつづくそれらの仕事は、どこか祈りに似ている。
わたしはただ座布団がほしかったのではない、と気づく。あの思い出のガウンと、誠実な作り手と、ずっと欲しいと思い続けている座布団を、点と点を結びつなげた、星座のようなものを眺めたかったのだ。そしてそれは夜空ではなく今わたしの手元でひかりをはなっている。
座布団を手に入れるまで何年もかかったが、こんなことが起こるから、いよいよ買い物をしようとする気が起こらない。感覚をたよりに、うっすらと望み続け、タイミングさえ逃さなければ、こんなふうにささやかな夢は叶い続けてゆくのだと確信したのだった。