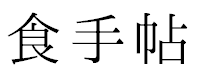2020/7/7
手渡された包みをひらいたら、きれいな色のつぼみが顔を出した。ひとつはなじみのある茗荷(みょうが)、そして黄色いつぼみは金針菜(きんしんさい)だという。包みは書道の反故紙。いつか目にした「山」の象形文字が書かれていた。
金針菜は、ヤブカンゾウのつぼみだそう。金針菜もヤブカンゾウも見たことがない。食べ方を聞いたら、みそ汁の実にしたり、炒めたり、とのこと。つぼみをいためる?と半信半疑で炒めて塩をふってみたら、ただそれだけでうっとりとするおいしさだった。ほんのり甘くて、わずかに粘りがあって、この味はなにかに似ている。夕暮れ時に、味の記憶をたぐりよせながら、ひとつ、またひとつとつぼみを食べ続ける。
おもいだした、花にらだ。高知では、にらにつぼみがついたものをその茎ごと食べる習慣がある。食べ方はやはりシンプルで、さっとゆでたり、炒めたり、お味噌汁の実にしたり。その花にらによくにていた。でも、この目の覚めるようなエネルギーはまたほかのなにかに似ているような気がする、としばらく考えた。そうだ、北海道の友から送られてきた行者にんにく。味もすばらしいが、味を超えたなにかしらが体にめぐっていくような感覚。そんなことを考えながらはじめての金針菜を食べたのだった。

茗荷は初物。今の時期と、夏のおわりと2回採れると聞いて、あわてて畑にいって茎の根本をすこし掘ってみたが、それらしきものは見つからなかった。茗荷は夏の香り。ちょうどつくってあった茄子の揚げびたしをゆで上げた麺にのせて、茗荷のみじん切りをたっぷりと散らして、大根おろしをのせた。
梅雨のさなかとはいえ、食卓の上はもう夏。季節はたしかに歩みを前にすすめている。ほんのいっときの旬は、ある日突然、目の前にあらわれ、そして知らぬ間に過ぎ去ってゆく。めぐる季節のなかの思いがけない出会いを、きっと僥倖というのだと思う。