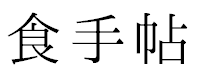2020/6/29
北の果てに住む友人と小包文通をしている。 いただいたらすぐお返事を、というよりも、季節のものがたくさん手に入った時に送る、という形のずいぶんとゆったりとした、年に数回のやりとりだ。
北海道と高知は植生も、採れる魚も、ずいぶん違う。北ヨーロッパに近い気候の北海道(梅雨もない)と、インドを感じさせる亜熱帯の雰囲気を持つ高知では、その違いは外国くらいある。 北海道では柑橘がとれないと聞いて驚いたこともあった。
今回の小包に入っていたのは、去年に続いてお兄さんが釣ったという立派なサクラマス、森でとったオオウバユリの根、お願いした白樺の枝、ハマナスの花、それからお手製の行者にんにくの醤油漬けとちいさな息子さんがオホーツク海でひろったシーグラス。毎回驚きに満ちた内容で、北海道はまるで外国、と思う。

小包は、寄宿舎に入っている魚好きの息子の帰宅にあわせて金曜日に届いた。その心遣いに感激しつつ、思いやりというのはこういう「ひとの事情をわすれないこと」を言うのだな、となんでもかんでも忘れてしまう私にとってはあこがれに近い境地。お手本にさせてもらおう、と思う。
お腹はきれいに出して塩してあって、とにかく立派!関東にいたときは鮭は日常的な魚だったが、高知に来てからは滅多に口にすることはなくなった。やはり北の魚なのである。嬉々として息子が巻き尺ではかると48センチ、重さは3キロほどか。「身が厚い!去年は45センチだったよね」などと話しながら、まずは3枚におろす。真ん中の背骨の部分に身が残るので(技術不足の証拠)、まずはその部分をさっと焼いて、「サクラマス焼けましたよー!」とフライパンごとテーブルにのせる。わらわらと家族があつまってきて「サクラマス!おいしい!」と感嘆の声をあげながら箸をのばす。
半身は、はじめてのフライに挑戦。タルタルソースは即席で。ヨーグルトとマヨネーズ、おろしにんにくに細かく刻んだ赤玉ねぎ、イタリアンパセリの刻んだのと塩、黒胡椒を混ぜる。フライなんて滅多にしないので、やはり大騒ぎで食べる。サーモンピンクの身のふっくらとしたやわらかさ。一年ぶりの味に恍惚とする。息子が「頭を半分に割って兜(かぶと)焼きにしてほしい」とせがむので、こちらもはじめてやってみる。骨が柔らかいのか、おそれていたほどの力勝負にはならず、割合簡単に割ることができた。
翌朝はお腹の塩が強くきいているところを焼いてほぐして、チャーハンに。そして夜は南蛮漬けにした。今回こそは冷凍して半解凍のお刺身「ルイベ」を試してみたかったし、白ワインの香りのムニエルも作りたかったのに、駆け抜けるように、あっという間になくなってしまった。こどもたちは、サクラマスは季節になると北海道から届くものだと思っているようで、去年送ってもらったときからどれだけ話題にのぼっただろう。
野草採取が特技の彼女は、森に分け入ったり、崖にのぼったりしてかなりワイルドに活動しているらしい。あるときは、食べたこともない山菜、行者にんにくがどっさり届いたこともあった。今回は行者にんにくの醤油漬けがびんにたっぷりと。「ごはんにそのままが道民スタイルです」と手紙に書いてあり、「道民」(北海道民のこと)、という言葉にノックアウトされる。
オオウバユリの根は、かつてアイヌのひとたちの主食で、刻んで臼でついたものをドーナッツ状に成型して、ひもで通して乾かして保存したとか。友人のすすめにしたがって、油でじっくり素揚げして塩をふると、ゆり根のほっくりした感じに、野山のものならではの野趣あふれる風味が加わって、しばらくすると、どきどきするような感覚が。調べてみたら、やはり民間療法で強壮、解熱作用に用いられたとか。なるほど、人体実験のようでおもしろい。

白樺の葉は、去年、ばさっと長い枝が段ボールに入って届いてからとりこになった。ヨーロッパを思わせる深い森の香り。お茶にしようと乾かしたら、部屋がこの上なくすがすがしい香りで満ちた。年に一度、北の果ての香りは、野草茶のブレンドにも加わる。
初めて見るハマナスの花は、瓶をあけると予想外に薔薇の香りが立ち上った。バラ科の植物でジャパニーズローズと呼ばれているそう。そのままグラスに入れてお湯を注ぐと、うっとりとするような薔薇の香りのお茶になった。薔薇よりも、薔薇らしい香りのような気がした。

北海道の地をまだ踏んだことはない。オホーツク地方に住む彼女と電話で話すと「流氷」とか「鮭の遡上(そじょう)」という耳慣れない言葉がときおり発せられ、どこか遠い国の話を聞いているような不思議な心持ちになる。スウェーデン人と結婚した彼女は、「ここに比べたらストックホルムは温かい」という。どこまでも遠くの話だ。ハマナスの香りに日本の異国を感じながら、いつかその咲く姿を見に行ってみたいと、とおく北の果てを思ったのだった。