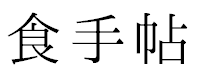2020/9/8
旅している人は特別な空気に包まれている。佇まいや言葉はしずかであっても、内部ではいろいろなものが活性化しているような、新鮮で、躍動感のある感じ。
家族が旅に出る。遠くから友人がやってくる。思いがけず旅人と出会う。それらがあるタイミングで立て続けに起きたとき、それがわたしにとっての「旅の時間」になる。
家族が旅から戻ってくると、あたらしいものが流れ込んでくる。その土地の空気をまとったおみやげもたのしみのひとつ。懐かしいもの、あたらしいもの、思いがけないもの。
もちろん一番たのしみなのが旅のはなし。記憶はどんどんうすれていくから、できるだけ旅の空気が濃いうちに話を聞く。空港から自宅までの40分は、さながら早回しの映画のよう。
友人が、パートナーとともに高知にやってきた。折しも台風のさなか、彼らの生き方とかさなるような、ドラマティックな登場だった。
12年前に出会って、ところどころで顔を合わせながらも、これまで個人的に会ったことはなかった。それでも、いつかきっと、ゆっくり話せる日が来ると思っていた。台風の、最後の強い風に吹かれながら、車を西へと走らせる。
こんなふうに再会すると、久しぶりのような、先週もあったような、不思議な感じがする。お互いに、知っているようで、知らない部分が、たくさんあって、とりとめもなく話しているうちに、だんだん輪郭がはっきりしてくる。それはどういうわけか、なつかしい感じにも似ている。
見知った町の風景も、よく行く食堂も、旅人を案内しながら、いつのまにか自分も旅人の目になってゆく。天気がどんどん良くなって、陽射しが強さを増してゆく。
もうすぐさようなら、というときに、白い服を着た彼らから、おみやげに、とわたされたのは謎の火山灰。(その意味はこれから明らかになってゆくのだろう)。わたしは、高知の旅のことをすべての感覚を使って思い出してほしくて、台所にあったすだちとにんにくを紙袋に入れて渡す。
どんな旅にも、伏線がたくさん張られている。きっかけ、後押し、決断。天候、目的、出会う人、そして手渡したり手渡されたりするもの。
明確な目的があったとしても、そしてそれが仕事であったとしても、帰ってきてから、あるいはもうすこし時間がたってから、当初の目的とはまったく別の「あのタイミングであの場所に行った意味」が明らかになってくる。
友人の 帰りの飛行機の時間が近づくと「もうすぐだ」と思う。見送りには行かないけれど、昨日の記憶をなぞりながら、彼らが空を飛んで帰ることを思い浮かべる。次に会えるのは、数か月後かもしれないし、10年後かもしれない。
一日は一瞬みたいだった。それでいて永遠のようにも感じられるのはどうしてだろう。たぶん、それは過去と、いまと、未来が、ひとところに集まった時間を過ごせたからなのかもしれない。そんなことを、台風の過ぎ去ったすがすがしい一日のはじまりに考えたのだった。