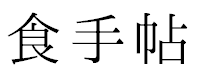2020/6/16
山のむこうに住まう方から、「あんずを採りにきませんか」と電話をいただいた。すべての予定を放り出していそいそと出かけると、目の前にそびえるのは30年以上前からある大木。見上げると見当がつかないくらい高い。遠くのひかりの中で梢が揺れている。
やや小粒のこのあんず、すこし黄色くなるとつぎつぎに落ちてしまうという。手が届く範囲は限られているので、木を揺らし、実を落としては、拾う。同時に伸びすぎた枝の剪定が盛大にはじまった。上からばさばさと落ちてくる大きな枝をよけながら、鈴なりについた実をどんどん摘み取る。まだ固くて緑色のあんずは、まるで青梅のよう。
箱にずっしりと詰まったあんずをいただき、夢のような気持ちで帰宅する。しかし、いつまでも夢見心地ではいられない。次なるプロセス、体力勝負の加工が待っているのだ。すぐにもろぶた(餅つきの時に使う木箱)にかさらならないように並べ、毎日風通しがよくなるように転がしたり、傷んだものを採り除いたりしながら追熟させること1週間。部屋は常にあんずの香りに満ちている。

生食には向かないので、すべてジャムにする。といっても我が家のジャム担当は夫。あんず8キロの種をナイフで取り除き、砂糖をまぶすところまでが私の仕事。一晩おいて、その後はあくをとりながら火入れをして、冷ます、を数回繰り返す。最後に瓶に詰めてしっかりと脱気処理。これで常温で保存がきく。
ジャムはふたをあけて早目に食べ切るのがおいしいから、半分は小瓶に入れて仕上げる。残りの半分は製菓用として大きめの瓶に。これだけあれば、今年の冬のシュトレンにも使えるかもしれない、と半年後をほんのすこしだけ想像する。
砂糖の量は、あんずの50%ほど。高知であんずを目にすることは少なく、かなりの希少品。山で自然に育ったあんずを山ほど手にするよろこびと、ジャム作りの大仕事。収穫と加工、これらはいつだってセットになっている。
ジャムの中でなにが一番好きかと聞かれたら、迷わずあんずと答える。香りの良さと、ねっとりとした食感、強めの酸味とそれに拮抗する豊かな甘み。濃い挑戦的な色も魅力だ。パンをしっかりと焼いて(あるいは焼きたてのバゲット)、発酵バターを分厚くのせ、その上に杏ジャムをのせたものには、単なるジャムトーストを超えた、ケーキをしのぐおいしさがある。それに、あんずにまつわる思い出もいくつか。
20代の前半、パリに旅行に行ったときに入った小さなチョコレート屋で、ジャムの瓶をみつけた。見るからに手作りの素朴な見た目で、ラベルは手書き。おいしいはずだ、と確信をもって持ち帰った。
その足でパン屋でバゲットを求め、スーパーに入りバターを買った。当時はよくヨーロッパを旅していて、旅行の時にはいつもちいさなまな板とナイフ、カトラリーとお皿を荷物に入れていた。3食外食では体がもたないのと節約の意味もあって、一日2食は散歩の途中で買ったパンやチーズ、果物を食べることにしていた。
ホテルの部屋でパンを切って、バターとあんずのジャムをのせたら、その圧倒的なおいしさに文字通り恍惚とした。この国の食には到底かなわない、そう思って打ちのめされた。フランスの果物は躍動感のある味で、酪農王国の発酵バターは信じ難いほど奥行きのある味だった。看板もないそっけないくらいの店構えのチョコレート屋は、のちに日本に店舗展開するジャン・ポール・エヴァンの店だったということを後で知った。
それから数年後、再びパリへ。一人旅の滞在先には、迷わずキッチン付きのアパルトマンを選んだ。朝の市場で1キロほどのあんず(あるいはプルーンだったかもしれない)を選び、スーパーで砂糖を買い、ワインを飲みながら天気の良い午後いっぱいジャムを煮て、日本から持参した空き瓶につめて脱気処理をした。それからパンとバターを買ってきて、鍋にすこし残ったジャムをのせて食べた。ただ砂糖と一緒に煮ただけでこんなにおいしいものができるなんて、フランスの果実は特別だ、とふたたび思った。
それから20年近くがたったいま、高知の山の上で採らせていただいたあんずは、また別の「特別さ」をまとっている。白い花がびっしりと咲くのを眺めた春、続く初夏の実りの豊かさ。そして惜しみなく手渡される好意。あんずジャムの物語は、数十年を経ていまだ螺旋階段のように私のまわりをめぐり続けている。