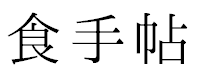2020/6/7
おしゃれが好きか、と聞かれたらほとんど興味がないように思う。それよりも大事なのは、着心地の良さや布の質、パターンや縫製の誠実さだったり、作り手がだれか、ということ。
体にあっているということは大事なことなのに、ないがしろにされがちだと思う。背の高さも、腕の長さも、質量感だってそれぞれずいぶん幅がある。それを9号とか11号とか13号、にまとめられてしまうのは不本意極まりない(既製服なんだからしょうがないけれど)。わたしはわりに背が高くてがっしりとしているので、いつも袖の長さが足りなくて、襟元がきつくて、「あなたの体形は規格にあっていません」と言われているようで、かなしかった。
買い物は不得手。なぜかといえば、好きなものやほしいものや自分に合うものがほとんどないから。特に服はその度合いが強くなる。かつてはいろいろなお店を回ってお買い物をしていていた。いっときはかなり傾倒したブランドもあった(きっといまも素敵な服をつくっているとおもう)。若く、十分なお給料をいただいていた20代の私は、洋服を店員さんから買うことしか知らずに、並んでいるものの中から選ぶことを当然と思い、そうしてたくさんの洋服を買っていた。自分なりに、質というものについて考えながら手にしたものだったので、つい最近まで、文字通りやぶれるまで10年以上着続けた。そして、やぶれるまで着たら、残念に思いつつも役目を終えたのだ、と処分していた。
ここ数年は、着るものに対するストレスがほとんど消滅し、むしろ歓びを得ている。というのは、古い友人に仕立ててもらっているから。仕立ててもらっている、というと聞こえがよいが、よくよく思い返してみると、試作ですと届いたものをそのまま譲り受けたり、誕生日のお祝いにと思いがけず贈られたり、インドのおみやげに渡したカディ(手紡ぎ手織りの布)が、うつくしく仕立て上げられて舞い戻ってきたり、となんだかずいぶん都合のよいことばかりだ。もちろん、正式にオーダーしたものもいくつかはある。
東欧の妖精のような独特の透明感を持つ彼女が仕立てる衣は、どれも洗濯機で洗え、しっかり直射日光に当てられて、畑での作業や家事はもちろんのこと、美術館に行くときに選ぶ服としても申し分ない。あらゆる意味で万能な衣。あまりに着心地がよいので、仕立てあがったばかりのものはよそゆきに、と思いながらも、つい畑や野草茶づくりの時に着てしまう。草の汁で染まってしまった下衣をどうにかならないか、と相談をもちかけて小包で送ったら、咲く前の山桜の枝で染め直したものが届いた。そのときの高揚は今もくっきりと思い出される。その後しばらく特別な衣として扱っていたけれど、またすぐに作業着となってしまった。つまり、きっと体がその衣を着ることを求めているのだ。大事なことをしているときに、大切な衣をまとうことは、理にかなっていると思う。
インドへ旅した時も、あらゆるケースを想定してスーツケースに服を詰めたけれど、手に取ったのは彼女のうつくしい指先から生まれた服だけだった。インドはすばらしい国で大好きだけれど、衛生、食べ物、移動、天候、どれをとっても過酷で緊張感の多い旅となる。そんなときになにより必要なのは「守られていること」。もとより衣服は体を保護するために生まれたように思うが、身が守られることは心が守られることにも通じる。「清浄」ということばが幾度も頭をよぎった。
袖を通した瞬間にせいせいするのは白い衣。うれしいのはうすくて簡素な衣のかろやかさ、袖丈や長さがいつも十分にある安心感。そして、いちばん大事なのは寝間着(無意識の領域におりてゆくときだから)。
やぶれても、ほつれても、よごれても、きつくても、衣にまつわるあらゆることを相談できる信頼。末永く大切にできることのよろこび。そんなことを日々、彼女の仕立てた衣をまとうことによって、学び続けているようにおもう。