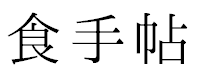2020/8/24
高知は自然が豊かだ。
海も、山も、川もすぐそこにある。
夏はとにかく毎日暑いし、こどもたちは夏休みで時間と体力を持て余している。海も、川も、夏のはじめにはしょっちゅう行こうと思う。
けれどいざはじまってみると、こまごまとした日常のことや、仕事のはかどりが気になりはじめる。加えて出かける準備(水着もった?タオルと水筒は?長靴じゃなくてウォーターシューズを履いて!)にかける労力を考えると、なかなか一歩を踏み出せない。
結局気が付くといつも夕方になってしまっている。
そんな中、後押しになるのが遠くから遊びにきてくれる友人。お茶を飲みながらおしゃべりして、ご飯をたべて、午後は川へ。
近くの川べりのキャンプ場は人でにぎわっているから、車で北へとむかう。山道にしか見えないやや鬱蒼感のある道を進んでゆくと、ひらけた川べりにたどり着く。
流れのゆるやかで浅い場所もある。そして、奥のほうへと行けば泳げるような深さの場所も。
ある夏、川で友人と過ごしたときのことだった。
大きな石の上にならんで、水のしたたる岩と、ひかりを受けてとうめいに繁る緑の木々を眺めながら、彼女は「ハワイみたい」とつぶやいた。ハワイといっても、ワイキキとか人気のビーチではない。むしろ手つかずの自然が残る森の中のイメージなのだろう。
わたしは、「高知の山奥がハワイ?」と笑った。でもしばらくして「なるほど」と思った。彼女は単に風景のことを言ったのではなくて、多分そこに満ちている、自然の生命力のことを言っていたのだ。
谷あいの川は、午後になると陽射しがとどかずとたんに気温が下がってくる。川の水は、ぎりぎり入れるくらいの温度。
それでも飛び込んではすこし泳ぎ、寒いさむいと言いながら、まだ陽のあたたかさを残している大きな石に戻ってくる。
水の中であおむけになって、空をふちどっている緑と、そのすきまから差し込むひかりを受けていると、時間や、空間や、そして日常もどこかとおい夢のように思えてくる。それらが「さしあたって生活してゆくための便宜的な枠組み」のように感じられる。
星を見る時もそれに近い感覚がある。けれど、川の水にからだを浸していると、よりダイレクトに、なんというか原始的で厳粛な、それでいてどこまでも自由な気分が湧きあがってくる。そこには、自然のすばらしさと、おそろしさと、人の手の及ばないダイナミズムがみちみちている。
山を聖域とみて、その中に身を投じて修行を続けることで、ある種の到達を目指す修験道。その世界のはしっこを、ほんのちらりと覗き見たような気がして、なるほど場の力というものは、それほどに強力なのだ、と腑に落ちた気もした。たしかに、川に身を沈めた瞬間に「禊(みそぎ)!」という感じがするではないか。
それにしても、と思う。
人の気配のしない自然の場所にいると、現実世界がどんどん遠のいていく。そして、もとの生活に戻ってゆくのがちょっと億劫に感じられてしまう。だから、長くはその場にはとどまらず、だれかと一緒に行くことが大事なのだろう。
そうして、日常生活にもどってゆくと、日々のくらしが自分の足場となっていることが、また特別に思えてくる。
家にもどるともう夕方。気持ちはすっきりとしていて、けれども体はすこし疲れている。
川の世界と、日常の世界のあいだにいるような感じがうっすらと残っていて、にわかには適応がむずかしい。それでも家族の「おなかすいた!ゆうごはんなに?」の声に追われながら、きゅうりや、なすを切りはじめるながら、この夏あと何回川にいけるだろうか、とぼんやりと思ったのだった。